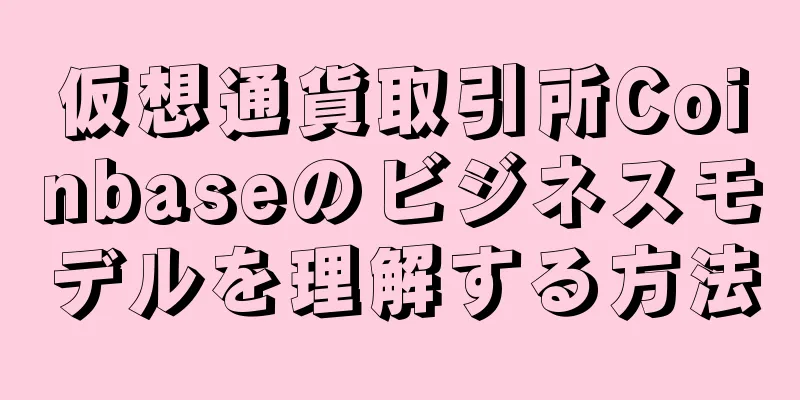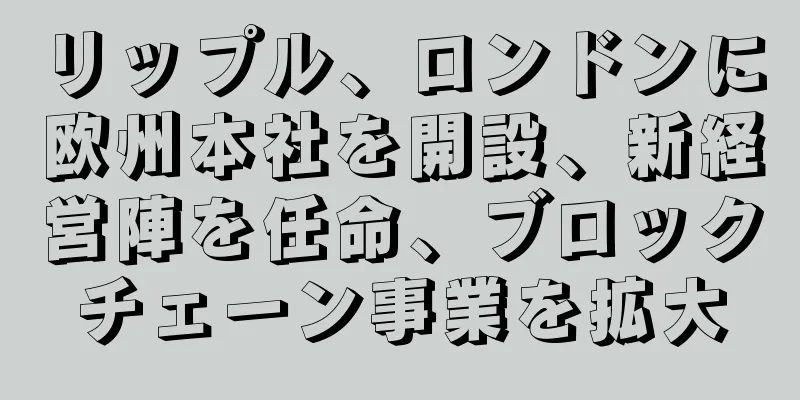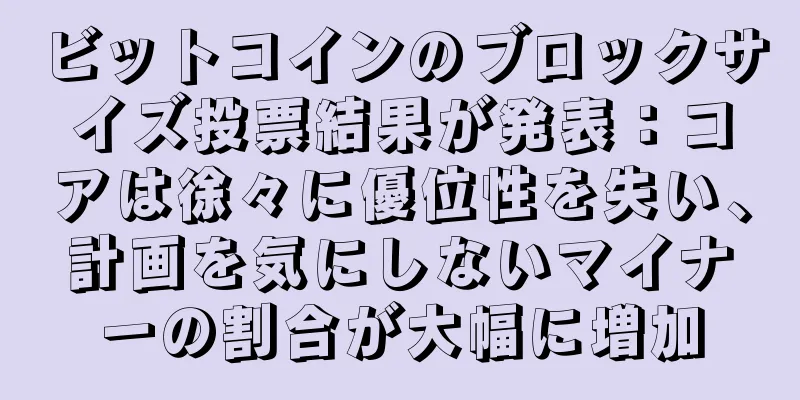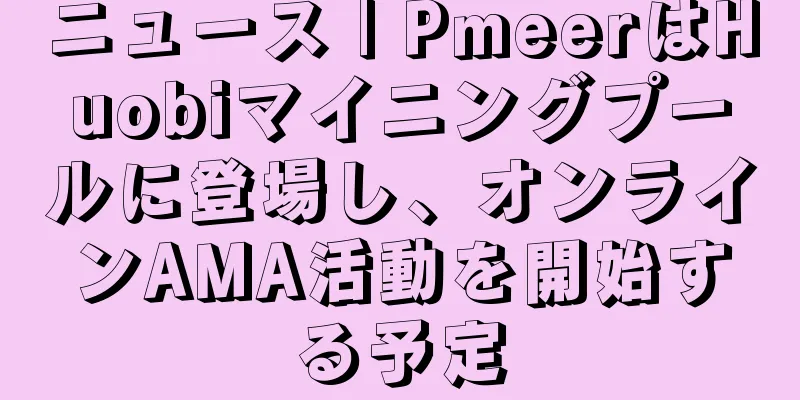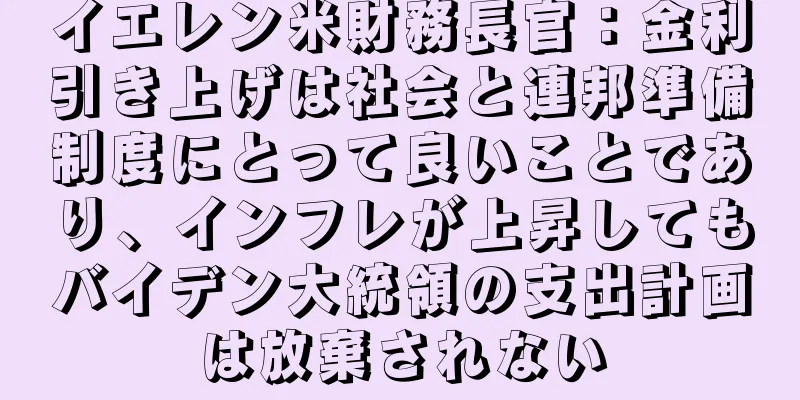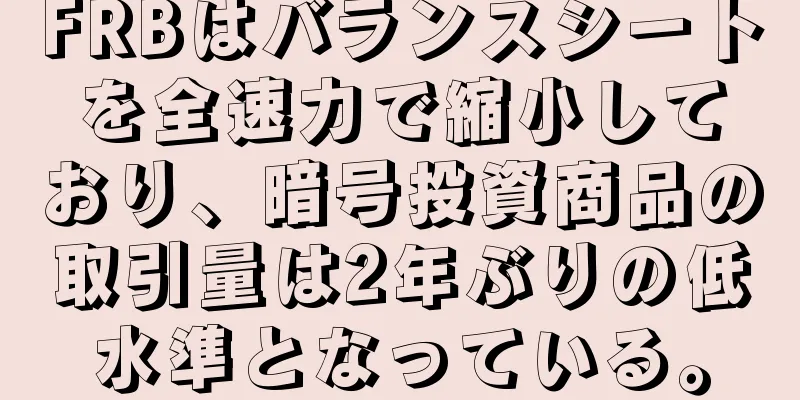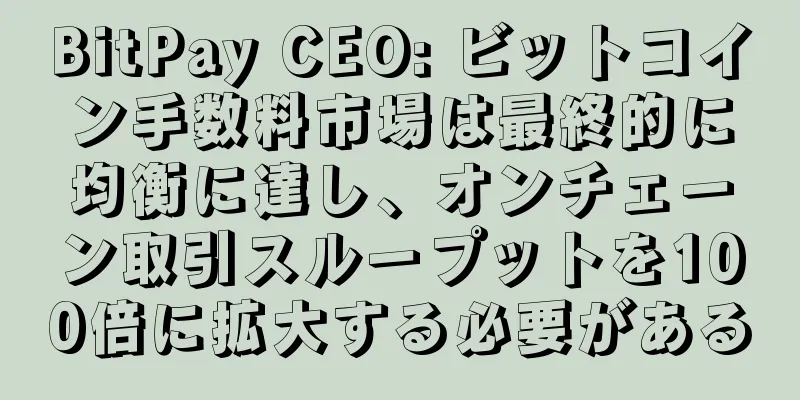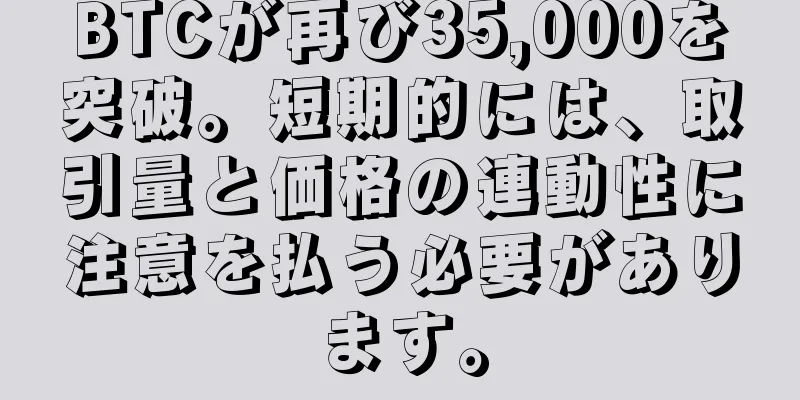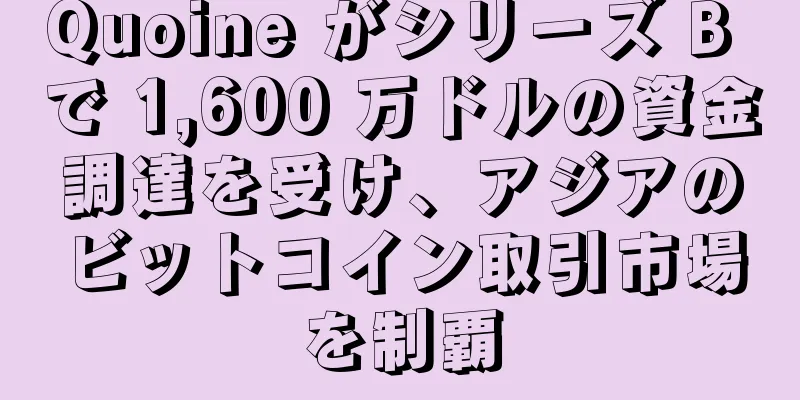連邦準備制度理事会(FRB)の利下げは株式市場を刺激するだけで、経済を刺激しない
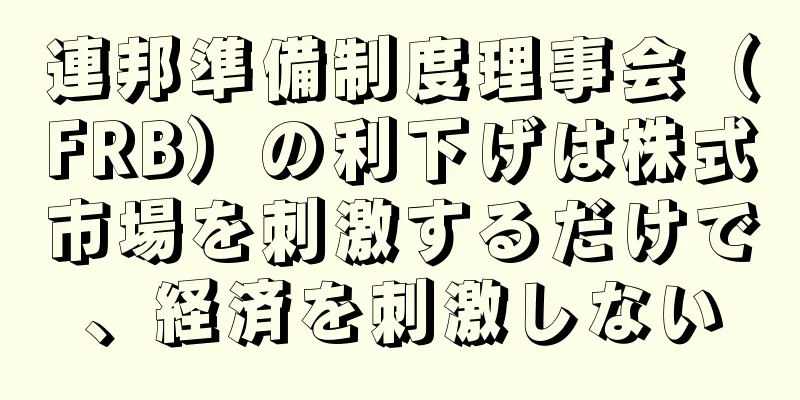
|
毎年8月、世界各国の中央銀行総裁が、カンザスシティ連邦準備銀行が主催する「シンポジウム」に米国中部のスキーリゾート地、ワイオミング州ジャクソンホールに集まる。 銀行家たちはこの機会を利用して、金融政策と、特にインフレを「抑制」し金融システムに適切な量の「流動性」を供給することにおけるその「経済運営」の有効性について議論した。 今年のシンポジウムは、経済が冷え込みの兆しを見せているものの、インフレ率は引き続きFRBの2%目標に向けて「着実に」低下していることから、FRBが「政策」金利を引き下げるかどうかというジレンマに直面している中で開催される。いわゆる政策金利は、米国(および世界のほとんどの国)の世帯と企業のすべての借入金利の下限を設定します。現在、この率は23年ぶりの高水準となっている。 8月初旬、連邦準備制度理事会が7月の会合で政策金利を引き下げないことを決定したため、金融市場はパニックに陥り、企業株の売りが始まった。その後、7月の雇用統計では、純雇用者数の急激な減少と失業率の上昇が示された。しかし、最新のインフレデータがインフレ率のさらなる(緩やかな)低下を示し、特にジェローム・パウエルFRB議長が9月の会合で中央銀行が金利を引き下げる方針を明確にし始めたため、市場は徐々に落ち着きを取り戻した。 パウエル議長は金曜日のジャクソンホール経済シンポジウムでの演説でもこの見解を繰り返した。 「我々は2%目標に向けた歩みを再開した。インフレが持続可能な形で2%に戻るとますます確信している…労働市場は以前の過熱から大幅に冷え込んでいる。労働市場が近いうちにインフレ圧力の源となる可能性は低いと思われる…労働市場の状況がさらに冷えることは望ましくないし歓迎もされない。今こそ政策調整の時だ。今後の道筋は明確であり、利下げの時期とペースは今後発表されるデータ、変化する見通し、リスクのバランス次第だ。」 パウエル氏はその後、FRBの金融政策により米国経済は景気後退を回避し、インフレは低下したと主張した。 「われわれの金融引き締め政策は、総供給と総需要のバランスを回復し、インフレ圧力を緩和し、インフレ期待の安定を確保するのに役立つ。」彼は、価格上昇は消費者支出の増加と供給不足の複合的な影響によるものだと考えている。これは事実ですが、どの要素が最も重要であるかが問題です。 インフレ期の研究のすべてではないにしても、そのほとんどが、過剰な消費者需要、政府支出、あるいは「過剰な」賃金上昇といった、当時の中央銀行が大幅な利上げを正当化するために使った論拠ではなく、供給要因が支配的であったことを示している。 しかし、パウエル議長は演説の中で、真の理由を示唆し、 「高インフレは、商品需要の急速な増加、サプライチェーンの逼迫、労働市場の逼迫、商品価格の急騰といった共通の経験を反映した世界的な現象である」と述べた。これはその後のインフレ率の低下も説明している。 「感染症流行による需給の歪み、およびエネルギー・商品市場への深刻なショックが高インフレの重要な要因であり、これらの要因の反転がインフレ率低下の重要な部分である。これらの要因の消滅には予想よりもずっと長い時間がかかったが、最終的にはその後のデフレに重要な役割を果たした。」 それでもパウエル氏は、中央銀行の「金融引き締め政策」は「総需要を緩和」することで機能しているという主張を主張し続けた。 パウエル氏はまた、中央銀行の金融政策が「インフレ期待を固定する」のに役立つという神話を繰り返し述べ、これがインフレ抑制の鍵だと言われている。しかし、これはナンセンスです。最近の研究では、「期待」はインフレにほとんど影響を与えないことが明確に示されています。連邦準備制度理事会の経済学者ラッド氏は最近、次のように要約した。 「経済学者や経済政策立案者は、家計や企業の将来のインフレ予想が実際のインフレの重要な決定要因であると考えている。関連する理論的および実証的文献を検討すると、この信念は極めて不安定な基盤に基づいており、無批判にそれに固執すると重大な政策ミスにつながる可能性がある。」 パウエル氏はまた、インフレを説明するために他の主流の概念も提唱し、それを使って「金融引き締め政策」を正当化した。 1つ目は、いわゆる「自然失業率」(NAIRU)です。この理論によれば、失業率はインフレを起こさずに経済成長を維持できるほど低いが、景気後退を示すほど高くはない。しかし、NAIRU は、測定が不可能な、はかない気まぐれな祝宴です。 NAIRU は、ケインズ主義の産物であるいわゆるフィリップス曲線に関連しており、労働市場が「逼迫」しすぎる場合 (つまり、失業率が NAIRU を下回る場合)、過度の賃金上昇がインフレにつながるとしています。賃金とインフレの間には「トレードオフ」が存在します。この理論は、1970 年代に経済が「スタグフレーション」(つまり、失業率の上昇、成長の鈍化、インフレの増大)を経験した際に、経験的に反証されました。 それ以来、いくつかの研究により、「曲線」はまったく存在せず、失業率、賃金、インフレの動向の間には相関関係がないことが示されています。実際、NAIRUに関するパウエル氏のコメントは、2018年のジャクソンホールシンポジウムでの発言と正反対だった。当時、パウエル氏は、通常の伝統的な「指標」、つまり経済が最適な速度で動いているかどうかを測るNAIRUや、借入コストが適切かどうかを測る自然利子率に従うことは、何の役にも立たないかもしれないと示唆した。 第三に、経済拡大を損なうことなくインフレを抑制する自然利子率があり、中央銀行はその利子率を測定してそれに従うべきであるという考えは、資本主義的生産の現実と矛盾している。タカ派のECB総裁イザベル・シュナーベル氏でさえ、「問題は、確信を持って予測できないということであり、それは運用が極めて難しいことを意味している…問題は、それがどこにあるか正確に分からないことだ」と認めた。 (!) 明らかに、これらの調和のとれた非インフレ的成長の自然率は絶えず変化しています。 「星を頼りに航海するのは簡単そうに聞こえる。しかし、星の位置に関する我々の最善の評価が大きく変化したため、実際に星を使って政策を導くことは最近困難であることが判明した。経験から、インフレと失業の関係について2つの現実が明らかになった。それは、私が最初に尋ねた2つの質問に直接関係している」とシュナーベル氏は続けた。第一に、星は我々が認識しているところから非常に遠くにあることがある。特に、失業率は、我々のNAIRU (u*)のリアルタイム推定値と比較して、経済の状態や将来のインフレについて誤解を招くことがあることが今ではわかっている。第二に、その逆もまた真なりで、インフレはもはや、労働市場の逼迫や資源利用への圧力の高まりを示す最初の、あるいは最良の指標ではないかもしれない。」そうなると、インフレは指標としては役に立たなくなる。 2024年のジャクソンホールシンポジウムは継続され、数人の著名な主流派経済学者が金融政策の有効性に関する論文を発表しました。論文の1つは、2020年のパンデミックによる暴落後の米国のインフレ急上昇に対するフィリップス曲線とベバリッジ曲線の説明を再検証している。ベバリッジ曲線は、求人が増えるとインフレが上昇し、逆もまた同様であることを示しています。 「両カーブに関する急上昇前のコンセンサスは大幅に修正される必要がある」と講演者は中央銀行総裁に語った。言い換えれば、既存の主流理論では、パンデミック後の最近のインフレの急増を説明できない。講演者は、失業率ではなく求人数に基づいた改訂版の曲線を提示しようとした。 それでも、パウエル氏は金融政策は成功したと宣言し、「全体として、パンデミックによる歪みの回復、総需要の抑制に向けた取り組み、そして期待の安定が相まって、インフレ率は2%の目標に向かう軌道に乗り、その目標はますます持続可能になっている」と述べた。そして、わずか3週間前には金融市場を不安に陥れ恐れられていた景気後退は考慮されていない。経済の「ソフトランディング」は依然として軌道に乗っており、力強い経済成長、低い失業率、低いインフレ率という「ゴルディロックス」シナリオが実現されようとしている。 前回の記事で、3週間前の市場の暴落はまだ景気後退の前兆ではないと指摘した。私にとって、重要な指標は何よりもまず企業利益です。これまでのところ、主要経済国の利益はマイナス領域には落ち込んでいない。 出典:Refinitiv、GDPで加重した5大経済圏の企業利益、私の計算 しかし、米国経済や他の主要経済国は、まだ危機を脱したとは言えない。 物価上昇率は「堅調」なままであり、中央銀行の目標を少なくとも約1パーセントポイント上回る見通しだ。 これはセミナーに参加した欧州中央銀行総裁たちが懸念していることでもある。 イングランド銀行のベイリー総裁は次のように述べた。 「我々が直面している問題は、この持続的な要因が目標通りのインフレ率の維持と一致するレベルまで低下するかどうか、そしてそれを達成するには何をする必要があるかだ。全体的なインフレショックが薄れるにつれて、持続的な低下は今や広く確立されているのか、それともマイナスの産出ギャップも必要になるのか、あるいは価格、賃金、利益率の設定においてより永続的な変化を経験し、金融政策をより長期間引き締める必要があるのか?」 ECBのチーフエコノミストのフィリップ・レーン氏も同様に、金融政策が「インフレとの戦い」の「最後の一マイル」で役割を果たせるかどうか疑問視している。 同時に、主要経済国全体で実質GDP成長率(特に実質一人当たりGDP成長率)は非常に弱いものとなっています。目立った拡大が見られたのは米国のみであったが、輸出と在庫を除いた場合の売上高の増加は1%に過ぎなかった。残りのG7諸国の経済は停滞(フランス、イタリア、英国)しているか、景気後退(日本、ドイツ、カナダ)に陥っています。他の先進資本主義経済国(オーストラリア、オランダ、スウェーデン、ニュージーランド)の状況もそれほど良くはありません。ほぼ全ての主要経済国において製造業は深刻な縮小に陥っています。 さらに、間もなく新しいアメリカ大統領が誕生し、輸入関税を記録的な水準まで引き上げて世界貿易を阻害し輸入価格を引き上げるか、あるいは企業利益に新たな税金を課すかのいずれかを望むだろう。どちらもアメリカ資本にとって良いニュースではない。 ジャクソンホールシンポジウムは成功を祝ったが、実際に明らかになったのは、中央銀行の金融政策が2022年のピークからインフレ率を下げるのにほとんど役割を果たさなかったということだ。生産量や投資の成長を達成する上でほとんど役割を果たしていなかった。そして、失業率の上昇や将来の生産量の減少を防ぐ能力はほとんどなかった。高い金利は多くの中小企業を破産に追い込んだり、さらなる負債を負わせたりするだけです。住宅ローン金利と家賃を最高値まで押し上げます。今金利を引き下げれば、経済ではなく株式市場が刺激されるだけだ。 |
<<: 複数のサイバー犯罪で告発されているテレグラムの創設者は、懲役刑を宣告されるのだろうか?
推薦する
ビットコインは7月に70%急騰、専門家は中国が規制対象に含めるべきだと示唆
7月に入るとビットコインは上昇し始めました。記者はビットコイン(中国)のKラインチャートから、ビット...
2つ目!ゼネラルモーターズ、ビットコインを決済手段として受け入れることを検討
テスラがビットコインで車を購入するという構想を発表した後、ゼネラルモーターズもそれに追随するようだ。...
F2PoolがHNSハンドシェイクマイニングを開始
F2PoolがHNSハンドシェイクマイニングを開始ハンドシェイクは、DNS (ドメイン ネーム シス...
イーサリアムPoSの根本的な欠陥は循環論法である
一晩中ビットコイン(BTC)は4万ドルを下回って推移した。イーサリアムの「統合」は延期されており、P...
X12 マイニングチュートリアル、Monero アルゴリズム
仕様:アルゴリズム: Cryptonight (Moneroと同じ)総供給量: 約1,800万 流通...
オランダの「クレイジーな家族」がビットコインに投資するために全財産を売却
オランダ人ディディ・タイフットゥとその家族新浪米株速報、北京時間19日、海外メディアの報道によると、...
イーサリアムの合併は誇張されすぎ?これら4つの物語から
暗号通貨界の太陽は9月16日に昇ります。Vitali kはマルベックワインを振って一口飲み、すべてが...
世界初の「完全に規制された」デジタル資産取引所、Biplusexがシンガポールで開始
Biplusex はシンガポール時間の水曜日に正式に立ち上げられ、パブリックブロックチェーン Eth...
ビットコインが今後も上昇し続ける5つの理由
現在、多くの人が投資目的でビットコイン分野に参入しています。たとえば私の母のように。以前、彼女は私が...
「ビットコインの優位性は永久に続くだろう。10年間の存続の歴史は他のどのコインにも匹敵しない」とモネロの主任開発者は語った。
時価総額で世界最大の暗号通貨であるビットコインは、2019年1月にジェネシスブロック10周年を迎え、...
マイニングマルウェアが大きな問題に:YouTubeもハッカーによるMoneroマイニングに利用されている
まとめCoinhive ウェブマイナーの使用は、YouTube やその他のサイトに掲載された Goo...
グレースケールは台座から落ちつつあるのか? GBTCはマイナスプレミアムが続いており、コインの狂った上場は下落傾向を止めることができない
呉碩 著者 |タン・シュウこの号の編集者 |コリン・ウー今年、グレイスケール・ビットコイン・トラスト...
AntPool の新機能をアンロックする時が来ました!
ユーザーのマイニング体験をさらに向上させるAntPoolはさまざまなインテリジェント管理ツールの開発...
ビットコインは死んだのか?残念ながらそれは単なる愚かな冗談です
Wired によれば、ビットコインは世界を変えるはずだったが、事態は変わった。今、再びこの重要な任務...
ビットコインの法定通貨化に反対!エルサルバドルの抗議者がビットコインATMを燃やす
ビットコインは機関投資家や富裕層に好まれる資産となったものの、通貨としてはまだ長い道のりがあるようだ...